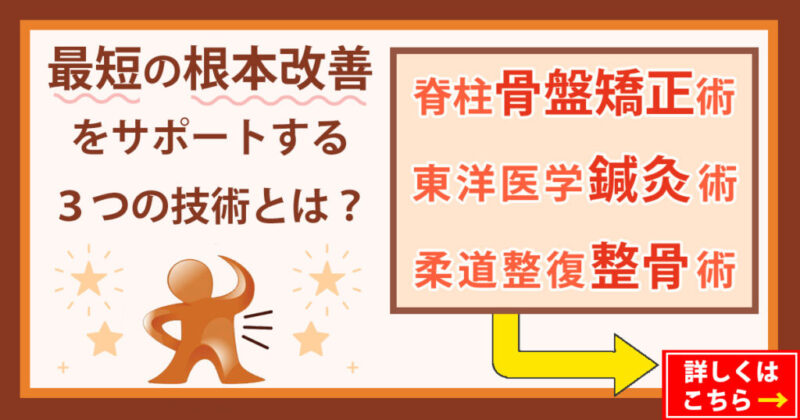ツボの達人ブログ
血について。岸和田まちの整体整骨院の考察
血について
そろそろ梅雨が明けそうです。
こんにちは!
岸和田まちの整体整骨院の宮河です。
前回、"気"についてお話ししました。
今回は、気の運搬役である"血"のお話を。
"血"とは、基本的には西洋医学と同じ「血液」という意味ですが、東洋医学では血液の成分や循環作用も含んだ、少し広い概念として捉えられています。
"血"と"気"は、相互に力を供給しあう関係で、どちらか一方の巡りが悪くなると、もう一方の機能にも悪影響を与えます。
"血"には大きく分けて二つの作用があり、全身の組織に酸素と栄養を与える"養営作用"と、髪や爪、筋肉、皮膚などの各器官に潤いを与える"滋潤作用"に分類できます。
"養営作用"によって与えられた栄養は、諸臓器に活動に必要な燃料や材料を巡らせ、その過程で"熱"が生み出されことから、"血"はその"熱"を運ぶ役割も担ってます。
"滋潤作用"には、全身に潤いを送ることで髪や筋肉、皮膚、爪などをみずみずしく保ち、また体の五感、特に視覚を正常に機能させる働きを持ちます。
これらの均衡が乱れると、様々な病態が出現します。
血虚
"血"の量が不足すると、"血虚"という病態となります。
これは、不眠、健忘、手足のしびれ、筋肉のケイレン、月経痛、爪が脆い、皮膚に艶がないなどの症状を伴います。
治療には、"養血"が用いられ、"血"の生成に関わる"腎"、"脾"、"肺"などの機能を高めるように働きかけます。
血瘀や血熱
"血"が乱れている場合は"血瘀"や"血熱"という病態が出現します。
"血瘀"では、肩凝り、皮膚が黒っぽくくすんで乾燥気味、しみやそばかす、便秘がち、血管がクモの巣状に浮き出るなどかあげられます。
治療法としては、"血"の流れを良くする"活血"があり、"血"の巡りを先導する"気"の滞りや不足、"熱"の過剰、"津液"の不足などを改善します。
具体例として、吸い玉が治療に用いられています。
"血熱"とは、"血"に熱がこもった病態で、鼻血がよく出る、出血が止まりにくい、血尿、月経過多があげられます。
治療には"清営涼血"が用いられます。
これは、"血"がもつ過剰な熱を冷ます治療法で、合わせて"肝"の蔵血作用や"心"の血液循環作用を高める治療も行います。
○これらの症状に心当たりがある方は、ぜひ一度、岸和田まちの整体整骨院にお越しください。ベテラン鍼灸師が貴方をお待ちしています。
(2018年7月2日)
気の不調について。岸和田まちの整体整骨院の考察
気の不調とは
雨で洗濯物が乾かず悪戦苦闘の毎日です。
こんにちは!
岸和田まちの整体整骨院の宮河です。
マンガや小説で、たびたび登場する"気"、東洋医学のなかでも特に重要な概念の一つです。
今回は、その"気"とそれらから見られる不調のお話し。
☆"気"とは、生命活動の根源的なエネルギーで、目に見えない無形の存在です。
例えば、"気"は体の中で電流のような役割を持ち、モーターとしての一面を持つ"血"や"津液"に動力として機能すると考えられています。
"気"は"腎"に生まれつき蓄えられている"先天の気"と、体の外から取り入れられた"後天の気"が結びついて生成されます。
後天の気には、食べ物から作り出される"水穀の気"と、呼吸から取り入れられる"清気"とがあり、一般的に"気"というと、この先天の気と後天の気が結びついたものを指し、"元気"(真気)とも呼ばれます。
体の中を巡る"気"は、その巡りに異常が生じると体に様々な病態を出します。
"気"の量が不足すると"気虚"という病態が現れ、体全体がパワー不足に陥ります。
症状としては、風邪を引きやすい、冷えやすい、胃もたれ、皮下出血しやすい、気力がない、体重減少などを伴う傾向にあります。
治療としては、"補気"を施します。
"気"の生成に携わる"脾"や"肺"の機能を向上して、"気"の量を増やします。
動きが乱れた場合は、"気滞"、"気陥"、"気逆"といった病態が現れます。
気滞
重い感じや張る感じのある症状を指し、神経質、胃が痛む、ゲップやオナラが多い、顔の火照りなどが挙げらます。
治療としては、"気"の流れを良くする"行気"を使います。
これは、"肝"の疏泄作用を高めるように働きかけます。
気陥
胃下垂、下痢が続く、頻尿、脱肛、立ちくらみといった症状が伴います。
治療には、"益気昇提"を用います。これは、"気"を補いつつ、"脾"の昇清作用や"肝"の疏泄作用を高めていくことをいいます。
気逆
"気陥"の逆の症状が"気逆"で肺の"気"が逆上すると、喘息やしつこい咳などが起こり、胃の"気"が逆上すると、ゲップや吐き気を引き起こします。
治療法は"降気"といい、肺の粛降作用に働きかけて、上がった"気"を下げて正常な"気"の状態に戻します。
○上記のような不調に心当たりがある方は、ぜひ岸和田まちの整体整骨院にお越しください。
ベテラン鍼灸師が貴方の体調にあった施術を施します。
(2018年6月29日)
五行説について。岸和田まちの整体整骨院の考察
五行説
ジメジメした日々が続きますね。
こんにちは!
岸和田まちの整体整骨院の宮河です。
以前に書いたお話しで"陰陽論"について語りましたが、
今回はそれを補う概念のお話しを。
☆五行学説という言葉があります。
筆者がよく読む異世界ファンタジー小説に頻繁にでるワードなんですが、
東洋医学では
「自然界や人間の体は木、火、土、金、水という5つの要素から成り立ち、各要素はある一定の法則に基づき、互いに関係を持ちながら、バランスをとっている」
という考え方をします。
これは、各要素がバランスよく機能してる状態を健康と捉えます。
このバランスは、''相生"と"相克"で保たれてます。
相生とはある要素が特定の要素を生み出す関係のこと。
五行的には、木は火を、火は土を、土は金を、金は水を、水は木を生み出す関係です。
でも、この相生ばかりが繰り返されると、生み出されるものが増え続けてしまい、バランスが崩れてしまいます。
その相生とは反対に働く力が相克です。水は火を消し、火は金を溶かすといった関係性です。
五行とは、この相生と相克が強まったり弱まったりしながら全体の調和を保っています。
そしてこのバランスが崩れると、体に不調が生じるのです。
この考え方を元に、五行色体表というものがあります。
細かく分類された表で、
例えば、金は肺(五臓)、大腸(五腑)、皮膚(五充)、鼻(五官)、咳(五変)、哭(五声)、悲(五志)、辛(五味)、魚臭い(五香)、白(五色)、秋(五季)、乾燥(五気)、夜(五時)といった具合です。
同じように、木、火、土、水も細かく分類されています。
これを治療に置き換えると、
皮膚に異常が現れた場合、皮膚は金のグループなので、肺や大腸などの機能の低下が原因と考えます。
その肺や大腸の機能低下を招いた一因としては、悲しみの感情が過剰になった可能性があると考えられます。
また、同じグループの鼻の症状や、咳なども併発してるかもしれません。
治療法としては、乾燥した気候に注意をし、辛味に属する薬や食べ物を取り入れるべきだと考えられます。
このように五行色体表は、1つの症状に対して、どの臓腑に問題があり、その原因は何で、どんな症状を併発するか、効果的な治療法は何かを推察する手掛かりとなります。
○岸和田まちの整体整骨院では、東洋医学を修めた鍼灸師が貴方の症状に合わせて治療を行っています。
興味がある方は、ぜひお越しください。
(参考文献:東洋医学 基本としくみ)
(2018年6月25日)
管鍼法とは。岸和田まちの整体整骨院の考察
管鍼法とは
今年は雨の降りかたが異常で怖いですね。
こんにちは!
岸和田まちの整体整骨院の宮河です。
よく、「患者さんに鍼って痛いやろ」や「衛生的にちょっと。B型肝炎とか怖いし」なんてお話を聞きます。
なので今回は、
日本で行われる鍼治療の方法
"菅鍼法"についてのお話し。
☆現在、日本で最も用いられる鍼治療の方法は菅鍼法です。
それは、"鍼菅"という筒状の器具を用いて、細く長い鍼を皮膚に刺す方法で、細くて柔らかい鍼を適切に刺すことができるので、痛みをほとんど感じずにすみます。
ちょいと昔は、ステンレス製の鍼菅を高圧滅菌消毒して使っていましたが、現在では、感染症予防や衛生面から、プラスチック製の使い捨ての鍼が主流です。
施術では、最初に経穴の位置を特定します。
個人差があるため、まず基準となる場所の周辺を触診し、皮膚の色味が違う箇所や乾燥、ザラつきがある場所、押圧時に痛みや腫れ、シコリなどの反応が強くでる所を経穴として決定します。
次に鍼を刺し入れる角度は、真っ直ぐや斜めなど、その経穴に適した角度を選択します。
鍼菅をやや強く経穴に押し当てると、筒の中から鍼が落ちて、瞬間的に皮膚に当たります。
ですが、鍼菅で皮膚を圧迫してる感触で、鍼が当たる感覚はほとんどしません。
その後、鍼菅後方から少し出ている鍼の端を指先で軽くトントンとして、鍼を少しづつ刺し入れます。
鍼菅を取り除き、さらにゆっくりと深く刺し入れていきます。
よく鍼をしてる最中に「ズゥンと響く」という言葉を聞きます。
これを"得気"と呼びます。
一方、鍼灸師は、筋肉の微かな動きや鍼が押し返されるような感覚を得ます。
これを"鍼を刺して気が至る"といい、"気至"と呼ばれます。
なお、得気が起こらない場合は、人為的にこれを得る技があり"候気"といいます。
東洋医学の治療法には"補瀉"という考えがあり、体の状態により、補(体に不足してるものを補う)したり、瀉(体に不要なもの、害のあるものを排除する)したりします。
鍼治療の場合も同じで、鍼の操作で"正気"を補したり、"邪気"を瀉したりすることで、不調を改善していきます。
○岸和田まちの整体整骨院では、ベテランの鍼灸師が施術を行ってます。
興味がある方は、ぜひお越しください。
(2018年6月22日)
陰陽論について。岸和田まちの整体整骨院の考察
陰陽論
そろそろ梅雨に入るのでしょうか?雨が少ないと野菜が高い!
こんにちは!
岸和田まちの整体整骨院の宮河です。
前回のお話しでは、"整体観"についてお話ししました。
今回は、そこから見出された"陰陽論"についてのお話し。
☆古代中国では、様々な自然界の法則を見出し、理論を確立していきました。
それは、人間の体の中にも自然界と同じ構造があるとする整体観を確立し、その中でも、もっとも基礎となる理論が"陰陽論"だとされています。
ざっくり説明すると、
「万物は、例えば夜の月とに昼の太陽のように、対立した性質をもつ二つの要素に分類できる」
といった考えです。
"陰"のイメージとしては、内に集まる/下降する/静か/重量が重い/濃度が濃い/吸収する/冷たい/暗い/水を生む/湿潤を生むなどが挙げられます。
本質としては"凝集"だと位置付けられるでしょう。
片や"陽"のイメージは、外に向かう/上昇する/躍動/大きな空間を占める/重量が軽い/濃度が薄い/明るい/熱を生む/乾燥するなどがあります。
本質としては、"放散"だといえます。
人の活動に置き換えると、
"陰"は鎮静、睡眠、滋養にあたり、
"陽"は興奮、活動、消耗となります。
これらは、優劣の関係を変化させてバランスを保っているのです。
例えば、朝に目が覚めると体は睡眠状態から活動状況へと切り替わる。
つまり、"陰"が優勢な状態から"陽"が優勢な状態へと変わり始めます。
夕方に近づくと疲れて活動性が鈍くなり、休息を欲します。
これは、"陽"が優勢な状態から、"陰"が優勢な状態へと移り変わるといえるでしょう。
このことから、どちらか一方が強くなり過ぎないようにバランスをとってることがよくわかります。
もし、このバランスが崩れたらどうなるでしょう?
本来は陰優勢の夜の時間帯に昼のように活動しつづけると、"陽"が過剰な状態に陥ります。
興奮し過ぎたり、目が冴えて眠れなくなったり、熱が過剰になって体が火照ったりしてしまいます。
このような"陽"が強すぎる事を"陽証"といいます。
反対に、陽が優勢な昼になってもダラダラと寝過ぎたりすると、"陰"が過剰になり、元気がでない、倦怠感がある、体の熱が不足して冷えやすいといった"陰証"となります。
"陰陽"のどちらか一方が過剰に盛んになったり、過剰に少なくなったりすると、バランスが崩れ、正常な状態ではなくなり、それが不調となって現れてしまうのです。
○"陰陽論"を用いる事で、体に起こる複雑な現象を総合的な視点で、
岸和田まちのでは鍼灸師が患者さんを分析しています。
興味がある方は、是非お越しください!
(2018年6月18日)
糖尿病も鍼灸治療で。岸和田まちの整体整骨院の考察
東洋医学的糖尿病への考察
長袖の服をそろそろ仕舞う時期になってきました。
こんにちは!
岸和田まちの整体整骨院の宮河です。
前回、現代病治療と東洋医学についてお話ししました。
今回は、それを踏まえて、生活習慣が原因の現代病である糖尿病のお話し。
☆現代病の多く、特に糖尿病は生活習慣と関連が深いです。
西洋薬で血糖値を下げる治療だけでは不十分で、生活習慣の改善が必要になります。
近年、成人の五人に一人はこの病気の疑いがあるといわれています。
なかでも生活習慣と関連があることがわかっている「2型糖尿病」が、糖尿病患者の約9割を占めています。
必要な栄養素が足りないので、体は痩せていて疲れやすく、たくさん食べたくなる傾向があります。
一方、胃腸から取り込まれたブドウ糖は行き場がなくなって血中に大量にとどまり、さまざまな合併症を引き起こします。
東洋医学的に診ると、ブドウ糖は活力を生み出し、体を構成する物質の元であることから"精"に相当します。
精は飲食物から胃腸を通して取り込まれ、"脾"の働きによって、体に役立つように処理されます。
糖尿病とは、この精がうまく利用されずに不足したり、過剰になったりした状態と捉えることができます。
これは体に必要なものを取り出す脾の働きが低下する"脾虚"の状態で、余分な精が溜まって"熱"に代わると"津液"が奪われて"陰虚"の状態になります。
すると、疲れやすい、風邪を引きやすいといった生命力の低下に繋がります。
東洋医学の治療では、こうした脾虚、陰虚といった状態や合併症の状態に応じて治療方針を立てていきます。
さらに、生活習慣の改善も不可欠です。
精を効率良く利用するには、日中の運動で余分なエネルギーの消費を促すことが必要となります。
エネルギーの蓄えを減らすために、摂取したものを体に溜め込みやすい夜間の飲食を控えめにすることも重要です。
また、ストレスや過労はブドウ糖の有効利用を妨げるため、日中は体を使ってしっかりと活動し、夜十分な睡眠を取ることが、ストレスや過労を減らすことに繋がります。
このように単に血糖値を下げるだけではなく、崩れた体のバランスを調整することが東洋医学的な治療の考え方です。
○岸和田まちの整体整骨院では、東洋医学的アプローチを駆使して治療に取り組んでます。
興味がある方は、ぜひお越しください‼︎
(2018年6月11日)