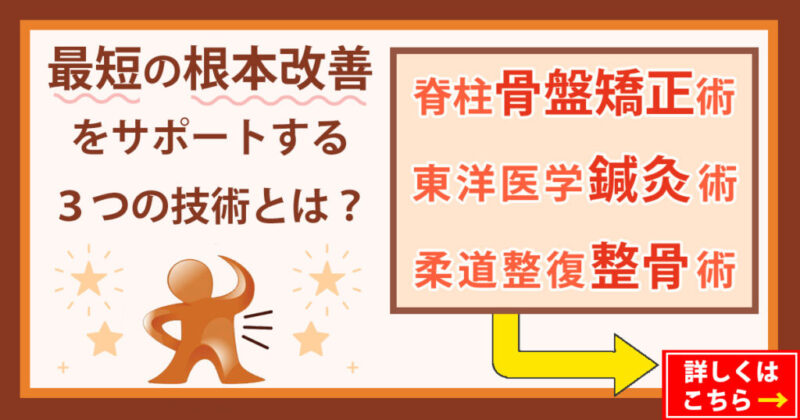ブログ&お役立ち情報
太ももの内側が痛いのはなぜですか?
こんにちは~!
岸和田まちの整体整骨院の山内です(^^)
5月も半分が過ぎましたね~
暑くなったかと思ったら
朝晩は寒くなったりしています。
体調管理がなかなか難しいですが、
お出かけの時は、カーディガンなど
羽織ものを忍ばせておいた方が
いいかも知れないですね~
さて、今回のテーマは
太ももの内側が痛いのはなぜですか?
です。
腰が痛い場合は股関節のストレッチや
大腿の内側を伸ばすことがあります。
その時にすごく痛がられる事があります。
ピリピリしたり、大腿の内側に
痛みが出たりとするので、
坐骨神経痛の症状に似ています。
○閉鎖神経痛
実は、坐骨神経痛と同じ種類の症状なのですが、
股関節、鼠径部、太腿の内側から膝に痛み、
太腿の内側に痺れる症状が出ることも
あります。
閉鎖神経の痛みは高齢の女性が
多いと言われています。
閉鎖神経に痛みが出る原因とは、
太腿の内側を支配している
神経が何か理由があり、何か障害を受けてしまい
神経痛が出てしている状態です
ここが硬くなってしまうと
このような症状が表れます。
皆さんはどうでしょう?
・鼠径や太腿の内側の痛み
・しびれやピリピリチクチク感がある
・歩いている時や太腿を閉じた時に
痛みがある
・ピン!となっているような痛みがある
・太ももの内側の感覚障害
思い当たる事はありましたか?
普段の姿勢の悪さや足を組む事が多い方、
お姉さん座りをされている方も
ご注意くださいね。
そして、先程にもお伝えしましたが、
高齢の女性の方に多いです。
腰や股関節の手術や骨盤周りや足の筋力が
落ちてしまったり、日常生活の中で
外閉鎖筋が緊張することで
大きな負担がかかってしまい、
閉鎖神経に痛みがでてしまいます。
○対策
スポーツからで痛みが出ている方は
太腿の痛みを改善するストレッチを
してみましょう。
ストレッチを続けることで
筋肉が伸ばされて、結構が良くなるほか、
痛みが早く改善することができます。
太腿の前側を伸ばすには
大腿四頭筋のストレッチをしてみましょう。
まずは、椅子を用意します。
では、椅子に座って頂き、
椅子に座った姿勢で両足を開きます。
両膝に手を当てて骨盤を前に倒します。
お相撲さんが土俵に上がって準備体操のように
しこを踏んでいる姿をイメージしてくださいね☆
このストレッチで内ももにつく内転筋群を
伸ばすことができます。
そして、姿勢を正しくを意識してみてくださいね(^^)

同じような症状でお悩みの方は是非、
岸和田まちの整体整骨院
までお越しください!
GoogleMAPを活用の方は
こちら
を検索。
岸和田まちの整体整骨院youtubeチャンネルで実際の施術の様子を見る事が出来ます。
(2024年5月16日)
吸玉の効果って何?
こんにちは~!
岸和田まちの整体整骨院の山内です(^^)
ゴールデンウィークも明日でおわりですが、
夏のような陽気で、
連休中に、来院された患者様の中にも
日焼けをして来られた方もいました。
だんだんと夏に近づいてきているので
日焼け対策と水分補給を行っていきましょう!
さて、今回のテーマは
吸玉についてお話していきますね(^^)
吸玉とは、カッピングとも呼ばれていて
民間療法の一つです。
身体の外から施術することで
筋肉や血液を刺激して、
体の不調な所を整えていきます。
吸玉は長〜い歴史があり、
紀元前100年頃中国で作られた書物の中には
吸玉を意味する言葉が記載されていたそうです。
ギリシャやエジプトでも動物の角を使ったり、
銅器などを使って施術したという説があります。
日本には6世紀頃から伝わったとされ、
江戸時代や明治時代といった近代から
行われてきました。
吸玉とは吸玉療法と言う通り
背中や患部にカップを載せて、
カップの中を一時的に真空状態にします。
そして、何分か置いてカップを外します。
シュポシュポとポンプのようなもので
吸い上げるのですが、
真空状態にする方法として、
火や香を使うものもあります。
皮膚を吸引することで患部の部分を
うっ血状態にして、体の内側の血液や汚れに
刺激を与えていきます。
うっ血するので、カップを取った後
くっきりと形が残りますが、
数日間から一週間くらいで消えていきます。
では、吸玉ってどんな効果があるのでしょうか?
○吸玉の効果
・血行促進
血管を拡張させることで、血行促進し、
老廃物の流れの改善
血液や十分な栄養を体中に行き渡らせます。
・睡眠の質があがる
吸玉で血行を良くすることで
心身ともに緊張が溶け、
交感神経と副交感神経の切り替えが
しやすくなります。
副交感神経を刺激されるので、
リラックス効果を高め、休息や睡眠の質を
高めることができます。
・疲労回復
吸玉で血行促進されるということは
温泉に入っているのと同じで疲れを取る効果も
あります。
血行の流れが良くなることで、
疲労物質の代謝、全身の疲労が
取れやすくなります。
また、全身に刺激を与えるので
腸にも適度に刺激となることで
便秘改善の効果も期待できます(^^)
便秘薬を飲んで、あまり効果が無かった方も
一度お試ししてみてはいかがでしょうか?

同じような症状でお悩みの方は是非、
岸和田まちの整体整骨院
までお越しください!
GoogleMAPを活用の方は
こちら
を検索。
岸和田まちの整体整骨院youtubeチャンネルで実際の施術の様子を見る事が出来ます。
(2024年5月5日)
腰が痛くなる原因は何ですか?
こんにちは~!
岸和田まちの整体整骨院の山内です(^^)
4月もあとわずかになりましたね。
ゴールデンウィークにまとめてお休みを
取られる方もいるかと思います。
家族で出かけたり、
また海外旅行に行ったり。
連休は関係なく、仕事やで!という方も。
ゆっくりした後や疲れた時に
腰が痛くなる方も多いのではないでしょうか?
さて、今回のテーマは
腰痛の原因についてお話していきますね!
腰痛になる原因と言っても色々な
原因があります。
子育て中の方は抱っこする体勢から
痛くなったり、デスクワークでお仕事で
長時間同じ体勢でいる時にも痛くなります。
年令問わず腰が痛くなる方はたくさんいると
思います。
そしてどの腰痛も共通点は
加齢と一緒に腰回りの筋肉や関節の衰え、
また、こわばりから柔軟性が無くなることが
原因とされています。
その痛い状態に無理な動きや体勢が
プラスされることで痛みが発症します。
腰痛にはどんな種類があるのでしょうか?
◯腰痛の種類
・筋性腰痛
筋性腰痛は、筋肉の使いすぎによって
起こります。
筋肉痛のような痛みで、
よく使った所に炎症が起きている状態です。
どんな方に多いかというと、
運送業や肉体労働、デスクワークなど
同じ姿勢が続いている方にも多いです。
痛いピンポイントが特定できるのが
特徴です。
・前屈腰痛
前屈腰痛は、背骨と椎骨の間にある
椎間板に問題があります。
物を拾う時、前かがみになった時
椎間板が圧迫されて痛みが出ます。
どんな方に多いかというと、
背筋が弱い人、猫背や前かがみになる
デスクワークのお仕事の方に多いです。
揉みほぐしをしても良くならないのが
特徴です。
・のけ反り腰痛
のけ反り腰痛は、
電車の吊り革を持ったり、洗濯物を干したり
赤ちゃんを抱っこしたりと腰が反り気味の姿勢
になった時に背中の後ろにある
椎間関節がぶつかることで痛みが出ます。
腹筋が弱いため反り腰になっている方に
多く、女性の方に多いです。
・おしり腰痛
おしり腰痛は、腰ではなく、
おしり近くにある仙骨の付け根の歪みや
炎症が原因で起こります。
産後の女性の方に多いです。
妊娠中に分泌されるホルモン作用で
緩んだ仙腸関節の靭帯が出産後に
正常に戻らない事で起こることが多いです。
☆ストレッチで腰痛予防しよう!
①立った状態でかかとをお尻に近づけように
して膝を曲げていきます。
②お腹に力を入れたまま、膝を後ろに引きながら
足の付根を前に突き出します。
③そのままキープします。
テレビを見ながらでも、
寝る前でも少しの時間でいいので
やってみて下さいね!
同じような症状でお悩みの方は是非、
岸和田まちの整体整骨院
までお越しください!
GoogleMAPを活用の方は
こちら
を検索。
岸和田まちの整体整骨院youtubeチャンネルで実際の施術の様子を見る事が出来ます。
(2024年4月28日)
腱鞘炎の時にやってはいけないこととは?
こんにちは~!
岸和田まちの整体整骨院の山内です(^^)
今日は暑かった!
お休みだったので外に出かけていましたが
半袖の方も多かったですね~!
さて、今回のテーマは
腱鞘炎についてです。
腱鞘炎とは手の使いすぎや手首や指の使いすぎによる関節に痛みが出る症状です。
腱は腱鞘というトンネルの中を走っているのですが、手を使いすぎてしまうと腱と腱鞘の間に
摩擦が起こってしまい、腫れてしまいます。
使いすぎてしまった後
安静にして休ませていれば、
腫れて痛みが出ている状態は治まりますが、
毎日の仕事や使いすぎてしまうと
腫れている状態は収まらず
痛みが伴ってきます。
県が引っかかって縮んだばねのように
指が開きにくくなる「ばね指」の症状も
現れてきます。
手のひら側に痛みが出るのはばね指で、
手をグーにして手を開いた時にかっくんって
遅れて伸びてくるような状態になり
症状が進んできてしまうと
指の付け根の痛みが出てきます。
親指が最も多く次に中指、薬指に出やすいです。
ひどくなると自分では動かしにくくなります。
指を伸ばす側の腱鞘炎は
拇指の付け根に症状が現れる
ドケルバン病です。
親指を他の指で握って、小指側に
手首を曲げると痛みが出てきます。
この状態では親指を伸ばしたり開いたりする
動作がしにくくなります。
◯腱鞘炎の予防
腱鞘炎が起きている時は、時々休憩を
はさんでストレッチをしたり
長時間続けて使う作業はなるべく
避けたほうが良いです。
キーボードを使ったりマウスを使う時に
手首をよく動かしたり、指先を使ったり
します。
その時に手に負担がかからないように
クッションを敷いたり、
手首を固定するサポーターと使ったりするのも
一つの方法です。
スマホを使う時には、片手で使うではなく、
両手を使うようにして、
片手にかかる負担を減らしましょう。
また、産後の子育て中の方は腱鞘炎に
なりやすいです。
抱っこをしたり、おむつを替えたり
お世話をする時に指や手を使います。
中々休ませる時間か難しいと思います。
無理せず、ご家族の協力をお願いしたり、
抱っこする体勢を変えてみたり
するだけでも負担のかかり方が
違ってくるかも知れません。
スポーツで痛くなりやすい時は
自分に合っていない、使い方や
ボールの握り方、良くないフォームのまま
続けていると手首に負担がかかり
腱鞘炎になりやすいです。
自分に合ったフォームや使い方で
手首に負担がかからないようにしましょう。
同じような症状でお悩みの方は是非、
岸和田まちの整体整骨院
までお越しください!
GoogleMAPを活用の方は
こちら
を検索。
岸和田まちの整体整骨院youtubeチャンネルで実際の施術の様子を見る事が出来ます。
(2024年4月25日)
春土用に気をつけること
こんにちは~!
ここ数日間は夏のような何とも春とは
思えないような日が続いておりますね😅
着替える時に塩が吹いていました(笑)
それほど汗かいちゃっていたんだな~と
思いつつ、水分摂れてないな~とか
体調管理気をつけんとあかんわ~とか
思いました。
さて、今回は春土用についてです。
夏、秋、冬もありましたね。
季節の移り変わり、
春から夏に少しずつ近づいていく
その期間が春土用です。
立夏前の18日間、今日から始まります。
この期間には、土いじりなどは避けて
ゆっくり過ごすのが良いです。
季節が変化していく期間なので
体の不調も出やすいです。
気圧の変化で不調が出やすい方、
胃腸が弱い方も気をつけておきたいです。
前回にもお伝えしたかも知れませんが、
部屋の掃除や断捨離をするのも良いです。
東洋医学では季節を体に例えて考える
そうですが、体の場所的に考えてみると
お腹(脾)の位置に当たります。
この時期には夏に向けて体を準備する
時間になります。
胃腸を休めて労ることで季節の変化に
対応しやすくなります。
食中毒を起こしやすかったり
アレルギー体質の方は症状が深くなる
事もあります。
暴飲暴食は避けていただいて
胃腸に負担がかからないようにしましょう。
また、体の怠さも出やすいので
お風呂に使って温まる、
できるだけ、睡眠を取るようにしましょう。
軽いストレッチをしたり、ウォーキングや
ヨガもおすすめです。
◯春土用は「い」のつくものを食べよう!
春土用は「戌」の日に「い」のつくものを
食べるといいとされています。
また、白い食べ物が良いです。
今の季節ですと、
いちごやいか、いも、いんげん豆、いなり寿司
イワシなど。
おもちとか、うどん、白米、
お豆腐もありますね。
夏に入る前にゴールデンウィークや梅雨の
時期もあります。
また、イライラからついつい
食べすぎてしまったり
濃い味付けのもの甘いものなど
食べすぎてしまうと余計に
胃腸に負担が掛かってしまいます。
食べ過ぎや飲み過ぎに気をつけて下さいね(^^)
腹八分目です!
特に食べる量が増えて、お腹が空いていないのに
食べ物を食べてしまっている時は
要注意です。
食べ物や飲みものは温かいものを
取るようにして下さいね~!
朝起きた時にお白湯をのんだりも
体が温まります。
同じような症状でお悩みの方は是非、
岸和田まちの整体整骨院
までお越しください!
GoogleMAPを活用の方は
こちら
を検索。
岸和田まちの整体整骨院youtubeチャンネルで実際の施術の様子を見る事が出来ます。
(2024年4月18日)
血圧が高いとなぜいけないのか?
こんにちは~!
岸和田まちの整体整骨院の山内です(^^)
4月も半分過ぎました。(早い!)
前半は雨の日も多かったですが、
暖かくなり、お花見に行かれていない方も
まだ桜も楽しめそうですね~。
さて、今回は高血圧についてです。
私は、どちらかというと血圧は低い方です。
母は血圧が高い方で血圧が高くなると
寝込むほどでした。
日本高血圧診断基準では、
収縮期血圧が140mmHg以上、
拡張期血圧が90mmHg以上の場合を
高血圧といいます。
高血圧は生命の維持にもっとも必要な
臓器が損傷を受けるまでに何年もの間
全く症状が現れない事が多いです。
そして「サイレントキラー(静かな殺し屋)」
と呼ばれています。
高血圧がコントロールされずそのままの
状態で放おっておくと、脳卒中、動脈瘤、心不全
心臓発作、慢性腎臓病などになるリスクが
高まります。
◯原因
高血圧は遺伝的体質からの方もいますが、
・塩分のとり過ぎ
・ストレス
・アルコールのとり過ぎ
・運動不足
・肥満
特に気をつけたいのが、塩分のとり過ぎです。
最近では、減塩の食品も多くなっていますが、
お醤油や味噌など和食によく使われています。
そして、お酒を飲む方はおつまみにも
気を付けたほうが良さそうです。
特に男女とも、60代の食塩摂取量が
多いそうです。
では、どんなことに気をつけたら良いのか?
◯気をつけること
・減塩を心がける
お醤油や味噌など減塩タイプの物を使い
薄味を心がける
・肥満の予防
若い世代から中年層の男性を中心に
肥満をともなう高血圧の割合が
高まっています。
肥満をともなう高血圧のかたは
拡張期血圧が先に上がり、
収縮期血圧も高くなります。
また、糖尿や尿酸、肝機能にも異常が
出ることがあります。
・定期的な運動をしよう!
有酸素運動を中心にするとよいでしょう。
ウォーキングやジョギング、水泳なども
良いですね。
30分位運動するのが理想的です。
体が慣れないまま最初から長時間ではなく、
少しずつ慣れていくのも無理をしないで
続けていけるコツではないでしょうか?
自分のぺースで始めてみましょう(^^)
・野菜や果物をとる
野菜や果物の中には体の中の塩分を
外に出してくれるカリウムが含まれている
ものがあります。
野菜は、
ほうれん草、にんじん、アボカド、枝豆、
切り干し大根
果物は、
バナナ、キウイ、メロン、干し柿など
バナナなどはミックスジュースなどにしても
良さそうですね。
・お酒を飲みすぎないこと
私は、あまり呑まない方ですが、
呑まれる方は週に一度は休肝日を。
おつまみもヘルシーなものを
食べるようにしてくださいね☆
そして、気になる方は血圧を
測るようにしましょう。
同じような症状でお悩みの方は是非、
岸和田まちの整体整骨院
までお越しください!
GoogleMAPを活用の方は
こちら
を検索。
岸和田まちの整体整骨院youtubeチャンネルで実際の施術の様子を見る事が出来ます。

(2024年4月14日)